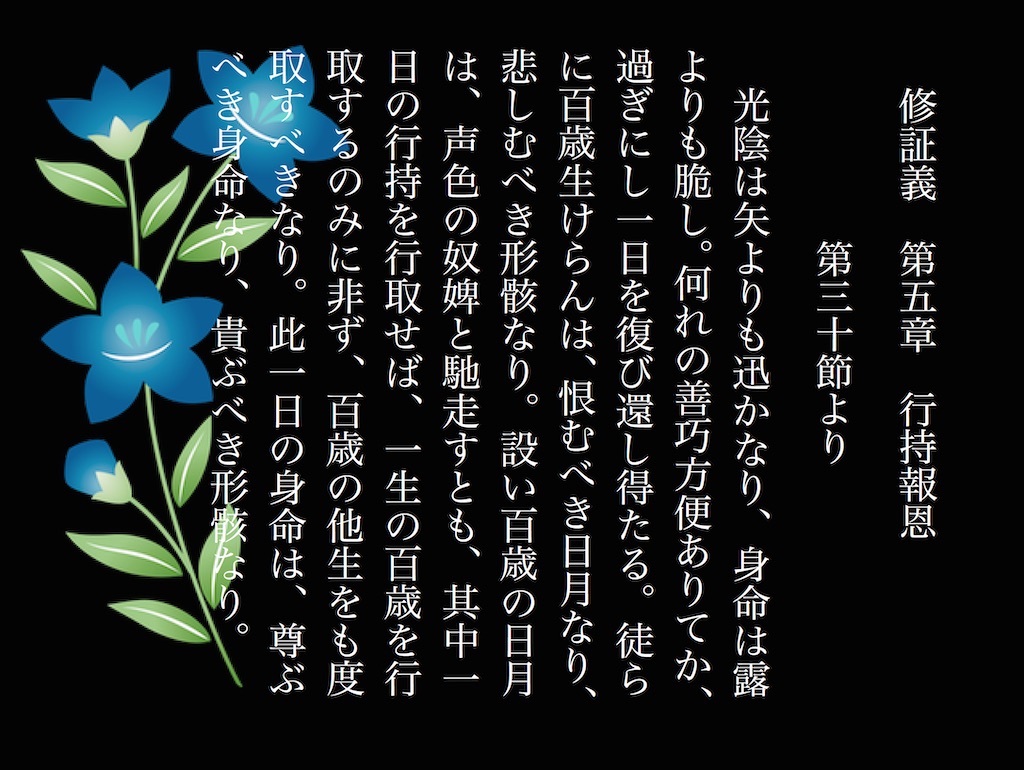修証義・道元
「修証義」は、日本曹洞宗を開いた道元の主著「正法眼蔵」の要文を再編集したものです。「正法眼蔵」は、曹洞禅の神髄が説かれた仏教思想書であり、日本における最高の哲学書であるという評価とともに、難解なことでも知られています。明治時代に入り曹洞宗内で一般の在家信者にも理解できるように「正法眼蔵」をわかりやすく再編集することの必要性が叫ばれ、曹洞扶宗会という在家信者の結社が中心となり「正法眼蔵」の要文の再編集が進められました。そして完成したのが「修証義」です。「修証義」は「正法眼蔵」の内容を理解するための入門書であるだけでなく、曹洞宗の教えがよくまとめられており、宗派のよりどころとなる経典として曹洞宗内でよく読まれています。道元は仏教の真理を正しく伝えたいという思いから「正法眼蔵」を著したといわれます。その態度は「修証義」にも貫かれており、「仏教とは何か」を考える時、「修証義」の内容は曹洞宗という一宗派を越えるものです。「生を明らめ、死を明らむるは、仏家一大事の因縁なり。(生とは何か、死とは何かを明らかにすることは、仏教徒にとって最大の問題です。)」この書き出しの文章が示す通り、「修証義」はすぐれた仏教の入門書でもあります。
この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。
パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。
下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下のページ画像をクリック又はタップすると朗読音声が流れます。
下のページ画像で現代語訳を確認してください。

<語句解説> をクリック又はタップすると、
本文中の重要語句について解説したページが開きます。
達磨大師が中国に伝えた禅と学風
インドから中国に禅を伝えた達磨大師は、釈迦(仏陀)から数えて二十八代目の仏教の後継者(第二十八祖)です。仏教では、釈迦(仏陀)以来、師の教えを完全に体得した弟子一人に、法を継ぐものとして仏陀の「衣鉢(袈裟と食器)」を継承させました。これを「師資相承・ししそうしょう」と言います。
五世紀の末にインドから中国に渡った達磨大師は、洛陽にある嵩山少林寺(少林寺拳法で有名)で、面壁九年の坐禅を行います。その後弟子に受け継がれたその禅は、長安、洛陽といった中国北部に広まった北宗禅と、中国南部に広まった南宗禅に分かれます。しかし北宗禅は次第に衰え、禅は南宗禅を中心に発展をしていきました。十世紀(唐の滅亡から北宋の成立の頃)には隆盛を極め、五家七宗(臨済、曹洞、潙仰、雲門、法眼及び臨済宗の分派である楊岐派、黄竜派)にその学風がわかれました。
栄西の臨済宗と道元の曹洞宗
1191年に宋から帰国した栄西は、臨済宗・黄竜派を伝え、日本臨済宗の開祖となりました。江戸時代に黄檗宗を伝えた隠元は、臨済宗・楊岐派の人です。一方四年間の留学の後、1227年に宋から帰国した道元は、曹洞禅を日本に伝え、日本曹洞宗の開祖となりました。
臨済宗を開いた栄西は、処世に長けた名誉欲の強い人でした。公的な僧侶の位(権僧正)を、貴族に賄賂を贈り得たりもしています。これに対して、慈円や藤原定家が日記で栄西の欲深さを非難しています。栄西の活動は常に政治的で、権力と結びつくことで禅を広めました。鎌倉幕府の庇護のもとで禅が広まっていったのは、そうした栄西の政治的な活動の結果です。室町時代において、幕府が後援する五山の臨済宗の禅僧が、様々な禅文化の担い手となったのも、そうした栄西の政治的な活動を受け継いだものだったのかもしれません。
道元は、内大臣・源通親を父に、太政大臣・藤原基房の娘である藤原伊子を母に持つという抜群の家柄に生まれました。出家しなければ高位高官は思いのままだったでしょう。しかし、道元はそうした世俗の栄誉をすべて捨てて出家します。比叡山へ上り天台教学を学び、栄西が開いた建仁寺で禅を修行した後、宋へ渡り如浄禅師のもとで曹洞禅を修します。道元の帰国に際して、師如浄は「権力に交わらず、深山幽谷に住み、一人でもよいから本当の弟子を育てよ」と伝えました。道元は、その言葉を守り、山深い福井永平寺にあって只管打坐を実践しつつ弟子を育てました。
臨済の栄西、曹洞の道元、どちらが宗教家として正しい道を歩んだのかと問われても、正しい答えなどあろうはずがありません。道元は入宋の前に建仁寺で修行しており、栄西の処世に長けた一面を聞き及んでいたと思います。それでも道元は栄西を非常に尊敬していたことが「正法眼蔵随聞記」の著述などからわかります。
臨済では壁を背にして座禅し、曹洞は壁に向かって座禅します。それは、さとりと人間との関わり方の違いです。人間が仏の本性に一致するために本人の自覚をうながすのが臨済の見性禅です。見性とは、人間に本来そなわる根源的な本性を徹見することです。一方、仏の本性を信じてまかせていくのが曹洞の黙性禅です。黙性禅では、一切の思慮分別を断絶してただ黙々と坐することによって、人が持つ仏としての心性があらわれるとされます。

今日という日
「修証義」は全三十一節から成ります。三十一節はあとがき的な内容ですので、ここで取り上げた三十節が最終節と考えてよいかと思います。
人生はあっという間で、人の命はいつどこで尽きるかわかりません。どうやっても、過去のあの日に戻ることはできません。人生に目的もなくただ長生きしても、後悔だけの人生であり、老い衰えた肉体だけが残ります。たとえ百年の人生が、周りの雰囲気に流されっぱなしで、欲望に支配され続けた人生であったとしても、今日という一日を大切に生きたなら、後悔ばかりの百年の人生が、今日という一日の中に包み込まれて浄化されるだけでなく、自分以外の他の人々の百年の人生をも包み込み、迷いの中から救いとるのです。今日のこの命は、まことに大切な命であり、まことに貴重な肉体です。
「生を明らめ、死を明らむるは、仏家一大事の因縁なり。(生とは何か、死とは何かを明らかにすることは、仏教徒にとって最大の問題です。)」という第一節の書き出しから始まった「修証義」は、この文章を結としてほぼ終わります。
「今日という日は、存在するものすべての過去、現在、未来の人生をつつみ込み、救い取る大切な一日であり、決してなおざりにしてはいけない。今日一日の生き方がそのまま仏の種まきであり、仏の命の行いである」
生と死は現象としては対極にあるはずなのに、生きるということは一歩一歩死に近づくことです。死という現象は生がなければ存在せず、生は死との関係においてのみ生です。生の中に死があり、死の中に生がある。まったく正反対のものが同居しているのが人生です。生と死は今日一日の私達自身の生き方の中にあります。
正岡子規の「病牀六尺」
正岡子規は、俳句、短歌といった日本の定形詩を改革して復興させ、それに近代文学としての位置を確立させた明治を代表する文学者です。子規は二十八歳の時、従軍記者として日清戦争に従軍し、その帰りの船中で喀血します。結核でした。根岸の小さな家で母と妹と暮らし闘病生活を続けましたが、結核菌が背骨を侵し脊椎カリエスを発症します。やがてすさまじい痛みで寝返りも打てないほどの重症となり、六畳一間の病床に寝たきりとなります。「病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである」子規は六尺の病床からみえるもの、六尺の病床で考えたこと、日常のありふれた小さなこと・・・・それを文章にして死の二日前まで新聞で実況中継しました。ある日、カリエスの激しい痛みの中、六尺の病床で子規は突然悟ります。「余は今迄禅宗の所謂悟りという事を誤解して居た。悟りという事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思っていたのは間違いで、悟りという事は如何なる場合にも平気で生きて居ることであった」

正岡子規・Wikipedia
ヴィクトール・E・フランクルの「夜と霧」
第二次世界大戦下、ポーランドのアウシュビッツ収容所に一人のユダヤ人精神科医が収容されていました。絶望と恐怖が支配する収容所で、彼は最後まで生き抜き生還を果たします。そして、収容所での悲惨な体験を精神科医の目を通して後世に伝えました。彼の名はヴィクトール・E・フランクル。彼の著した「夜と霧」は、これまで600万人の人々に読まれ、これからも世代を超えて読みつがれていくことでしょう。
収容所には時々デマが流れます。連合軍が攻勢に転じ来月にはこの収容所も開放される。収容所のユダヤ人たちにはそうしたデマだけが生きる希望でした。しかし、翌月になっても連合軍は来ません。希望は絶望に変わり、ある人は高圧電流の流れる鉄条網へと全力で走っていき、ある人は皆が寝静まった夜中、天井の柱に作業中に隠し持ったロープをつるし自らの命を絶っていきました。 以下「夜と霧」からの抜粋です。
「必要なのは、生命の意味についての問いの観点の変更である。われわれが人生に何を期待できるかではなく、人生がわれわれに何を期待しているかが問題なのだ。そのことをわれわれは学ばなければならないし、絶望している人に教えなければならない。われわれが人生の意味を問うのではなく、われわれ自身が人生から問われる存在なのである。人生はわれわれに毎日毎時問いを出しつづけ、われわれはその問いに詮索や口先ではなく、正しい行為によって応答しなければならない。人生は結局、人生の意味の問題に正しく答えること、人生が各人に課す使命を果たすこと、日々の務めを行うことに対する責任を担うことに他ならない」ヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』霜山徳爾訳

参考文献
鎌田茂雄著「禅とはなにか」講談社学術文庫
山川宗玄著「禅の知恵に学ぶ」NHK出版
竹村牧男著「日本仏教のあゆみ」NHK出版
鈴木大拙著「禅と日本文化」岩波新書
禅の入門書としてお勧めするなら、鎌田茂雄著「禅とはなにか」講談社学術文庫と山川宗玄著「禅の知恵に学ぶ」NHK出版です。
華厳経の参考図書でも触れましたが、禅を学ぶなら鎌田茂雄著「禅とはなにか」講談社学術文庫は必読の書と思います。軍人の家に生まれ、陸軍士官学校予科で終戦を迎えた著者は、終戦によりそれまでの価値観が一挙に崩れ去り、茫然自失の中に鎌倉円覚寺で参禅し、何とか心の平安を得ようともがき苦しみます。第一章「禅との出会い」では、著者自身が仏教学者として歩んで行くことになった軌跡が禅との出会いを通して語られ、もうはるか遠くになってしまった終戦直後の若者の心の葛藤が描かれています。この本の素晴らしいところは、仏教・禅の名僧名著の言葉をあげながら、それを現代人が如何に生きるかの礎として解説してくれる所です。以下一文をご紹介します。
臨済義玄が「仏を求め、法を求むるも即ち是造地獄の業」と述べたが、まさに無所得・無功徳なるところに、宗教の第一義が存在しなければならぬ。「無功徳」のところに、無尽の宝蔵が備わるのだ。それでは無所得・無功徳の生命を支えるものは何か。それは無限の努力に他ならない。「ため」にする努力ではない。求めて求めない努力に他ならない。仏陀の最後の言葉は、「不放逸にして精進せよ」であった。怠らないで努力するという、この簡単な言葉の中に人生の無限の真理が含まれている。理想は実現できないから理想であり、実現できない理想に向かって、一歩一歩努力していくところに人生の意義がある。道元が「学道の人は、後日を待ちて行道せんと思うことなかれ。ただ今日今時をすごさずして、日日時時を励むべきなり」といわれたことは、千古の名言である。 鎌田茂雄著「禅とはなにか」より
著者鎌田茂雄氏の文章は、読者にこびない芯の強さがあります。ですから時として読者自身が一喝されるかの如く感じる箇所があるかもしれません。Wikipediaで検索すると、その人物について「在学中より舌鋒鋭い事で知られ、教師であろうともその怠惰な仏教学への姿勢を追求する事には容赦なかった」とありました。然もありなんです。
山川宗玄著「禅の知恵に学ぶ」NHK出版は、「こころの時代」の番組テキストです。山川宗玄老師は、臨済宗妙心寺派の僧侶で、修行の厳しいことで知られる岐阜県美濃加茂市にある正眼寺の住職です。このテキストは、禅についてよくまとめられているだけでなく、禅の修行が実践者としての立場から具体的に紹介されています。このテキストを読み進める中で著者の次の言葉には強い感銘を覚えました。「修行道場は、あえて苦労をさせる場です。苦労に苦労を重ねることで工夫が生まれ、無心仏心の世界に入ることができるのです」
これを読んだ時思い出したのが、世阿弥が風姿花伝で繰り返し述べていた「芸を極めるにおいて工夫を怠るな」、宮本武蔵の五輪書における「能く能く工夫あるべし」この二つの言葉です。世阿弥は厳しい稽古を繰り返す中での工夫の大切さを次のように語っています「物数を尽くし、工夫を極めて後、花の失せぬ所をば知るべし(数多くの芸風の演目を稽古し尽くし、工夫を極め尽くした後、芸の花・魅力がなくならない境地がわかるであろう)。宮本武蔵は朝鍛夕錬すること、つまり厳しい稽古を毎日継続する中で、工夫することの大切さに気づいています。武蔵の実戦的兵法は鍛錬と工夫の賜物です。武蔵はその著「五輪書」の中で「武士は兵法の道を確実に会得し、その他武芸をよく鍛錬し、武士として行う道に明るく、心に迷いがなく、何事も常に怠らず、心意二つの心を磨き、観見二つの目をとぎ、少しもくもりなく、迷いの雲の晴れた所こそ、真実の空であると知るべきである」と述べています。乱世を一人で生き抜いてきた男が到達した世界観ともいうべき境地は、このようなものだったのです。
工夫など当たり前ではないかと思いがちですが、苦労、稽古、鍛錬を重ねる中で生まれる工夫こそが本物の工夫です。また「工夫とはすなわち無駄を省くことです」との著者の言葉にも、目からうろこが落ちた気がしました。