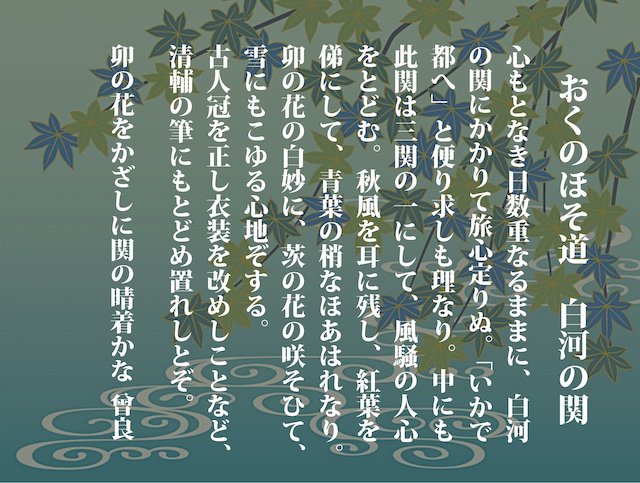おくのほそ道「白河の関」・松尾芭蕉
白河の関は、古くからみちのく(奥州)への入り口とされ、多くの歌人が歌に詠んだ歌枕の地です。芭蕉は「白河の関」で、いよいよみちのく(奥州)への旅が始まるのだという引き締まった気持ちと、初夏の白河の地を卯の花とむばらの花がその名の通り白さで飾っている様子を文章にしています。
この解説サイトは電子書籍にリンクが貼られていますが、電子書籍をダウンロードせずに読まれる方(主にスマートフォンで読まれる方)のために、電子書籍の表紙とページの画像、語句解説、朗読音声などが含まれています。
パソコン(Windows・Macintosh)又はiPadで読まれる方は、電子書籍をダウンロードしてお読みください。ダウンロードサイトは右サイドバーに表示されたURLをクリック又はタップすると起動します。
下の画像は電子書籍のページを画像で掲載しています。

下の画像をクリック又はタップすると、朗読音声が流れます。
下の画像で現代語訳を確認してください。
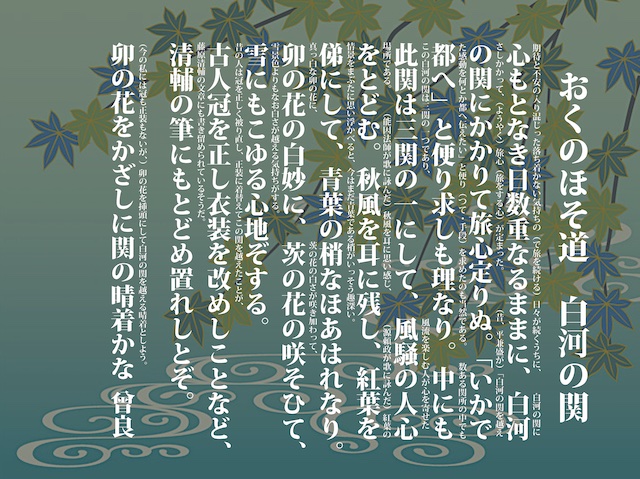
本文中の重要語句を解説しています。
下の<語句解説>をクリック又はタップしてください。

「心もとなき日数重なるままに、白河の関にかかりて旅心定りぬ」
期待と不安の入り混じった落ち着かない気持ちの(で旅を続ける)日々が続くうちに、白河の関にさしかかって、(ようやく)旅心(旅をする心)が定まった。
「白河の関」冒頭の文章は、おくのほそ道の中でもひときわ印象に残る名文です。
芭蕉はこの名文を、旅を終えた後に何度も推敲を重ねて作りました。その時、この名文に自らの人生を重ね合わせていたのだと思います。
「若い頃より俳諧の道に入り、俳諧師として一旗上げようと江戸に出て、弟子も増え有名にもなったが、しょせん弟子に養われる心もとない毎日だ。今こうしてみちのくを旅した記憶をたどって書き綴っているが、俳諧紀行小説という新しい文芸スタイルを確立し、新たな収入の道を得られないだろうか」という思いがふつふつと湧き上がってきたのです。
「おくのほそ道」という作品は、芭蕉にとって人生の白河の関でした。
「読者が感動してくれるものに最高の価値がある」
芭蕉はおくのほそ道の前に「野ざらし紀行」「鹿島紀行」「笈の小文」などの紀行文を書いていますが、それらは出版を目的としたものではなく、弟子たちや俳諧仲間に読ませるためのものでした。
時代は元禄という江戸時代最初のバブル景気です。大阪では井原西鶴が俳諧師から浮世草子作家に転向し、「好色一代男」「日本永代蔵」などのヒット作を連発して大成功をおさめていました。芭蕉に「俺だって」という気持ちが湧かないはずがありません。
交通手段もほとんど徒歩に限られ、治安もよくなかった当時は、庶民が気軽に旅をできる時代ではありませんでした。特に奥羽地方は「辺土」と呼ばれ未開の地も多く、まだ見ぬ景色を伝える紀行文は必ず大きな反響があると芭蕉は見込んでいたのです。
ただし、売れる紀行文とは、読んで面白い、感動する紀行文でなければなりません。見たまま、ありのままを正直に伝えるだけの紀行文など面白くもなければ、感動も生まれません。いかに読者に面白いと思ってもらえるか、いかに感動を与えられるか、そこにこそ紀行文の商品価値があります。
芭蕉が白河の関(とされる地)にさしかかった時、そこは関所どころか歌枕の地であることを感じさせるようなものは何もない山中でした。その何もない山の中を芭蕉は類い稀な想像力で古の歌人たちが歌に残したイメージ以上の地に仕立てあげたのです。
曽良日記によると、芭蕉たちが白河の関にさしかかったのは、旧暦四月二十一日(陽暦六月十日)です。
卯の花の白妙に、茨の花の咲きそひて、雪にもこゆる心地ぞする。古人冠を正し衣装を改めしことなど、清輔の筆にもとどめ置かれしとぞ。
卯の花も茨の花も確かにこの季節(初夏)に真っ白な花を咲かせます。けれども、これは白河の白をイメージした芭蕉の想像上の景色に他なりません。そして、その何もない山の中を、芭蕉は、人が冠を正し、正装に着替えて通過するほど格式の高い場所として描き上げました。
一方、この文章を読んだ読者は、白河の関を芭蕉が文章で描いた、まさにそのような場所として心に刻むのです。
芭蕉が「おくのほそ道」に込めたもの。それは散文と俳句を融合させた紀行文によって「いかに読者を感動させるか」でした。
松尾芭蕉の代表作というだけでなく近代日本を代表する書物の一冊である「おくのほそ道」は、出版ビジネスとして成功させたいという芭蕉の切なる願いから、いかに読者を感動させるかという視点に基づいて生まれた一冊です。しかし推敲に五年を費やした芭蕉は、結局「おくのほそ道」の出版を自分の目で見ることなく病気で亡くなりました。
もし芭蕉が「これまでの集大成として、自分の納得のいく最高の作品をつくろう」という思いだけで「おくのほそ道」を執筆していたなら、後世ここまでの高い評価が得られる文芸作品となっていたかどうか、はなはだ疑問です。
「自分が満足するものに最高の価値がある」という思い込みを捨て、「読者が感動するものに最高の価値がある」という発想に転換したからこそ、「おくのほそ道」は近代日本を代表する文芸作品となったのです。